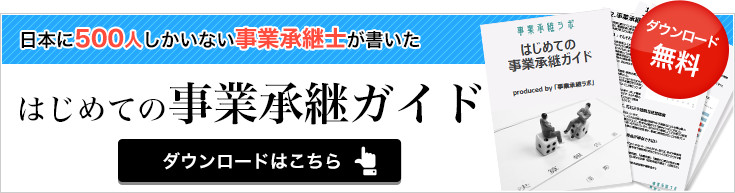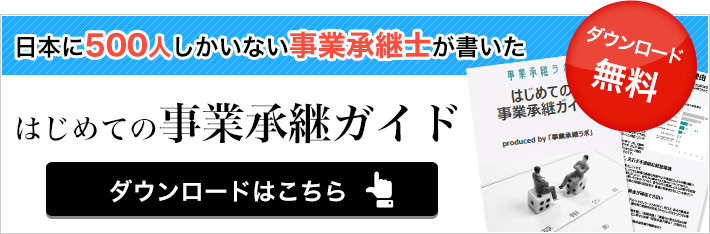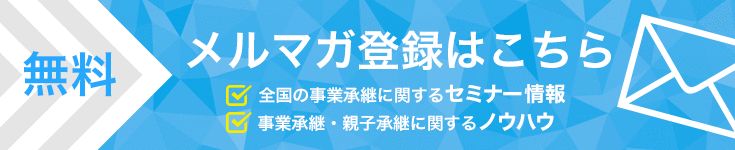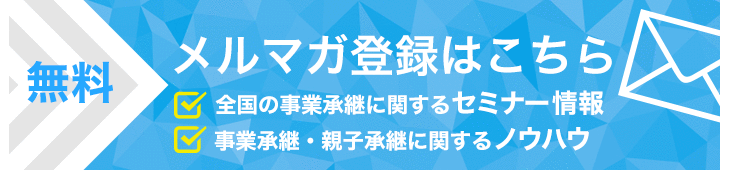現代社会は、流動的で激しく変化します。特に現在は、IT化が急速に進んでおり、IT化の波にのまれてしまうのか、素早く適切に対応できるかどうかが会社の命運を左右すると言っても過言ではありません。そこで今回は、コダックと富士フィルムの対比を参考に、変化に正しく対応するにはどのような経営が求められるのかを紹介していきたいと思います。
コダックと富士フィルムの「フィルム販売」
コダックも富士フィルムもフィルム販売を柱に事業を展開していました。とりわけ、コダックは先進的な技術と革新的なマーケティングで銀塩写真の領域で世界的なブランドを確立し、世界に君臨していました。
ひと昔前、「コダック・モーメント」といえば、保存して堪能する価値のあるシャッターチャンスのことを意味する言葉になっていました。しかし今日、この言葉は、経営者に対する警告の意味合いを強めています。「市場に破壊的変化が忍び寄ってきたら、立ち上がって対処しなければ大変なことになる」という戒めとなったのです。
かつて写真フィルムは、世界でも4社しか製造できない商品でした。この市場は、アメリカのコダック、ドイツのアグファ、日本の富士フイルム、コニカの4社の寡占市場となっていました。そのために、上位企業はかなりの利益を得ていましたが、銀塩式の写真フィルムにとって代わるデジタル写真の登場でフィルム市場に大きなパラダイムシフトが起きました。
フィルム写真からデジタル写真への変換に対する両社の対応の違いが、会社の「破綻と成長」の大きく異なる結果をもたらしたのです。

コダックの対応と誤り
実はコダックは、商品化されなかったものの1975年には世界最初のデジタルカメラを開発し、その後、世界初のデジタル一眼レフカメラを 1999年に市販していました。つまり、コダックはデジタルカメラの時代潮流を完全に予測し開発を行っていたのです。しかし、デジタル化への対応に力を入れておらず、それには理由があります。
①好業績企業の傾向
それは、デジタル写真ではそれほど利益が上がらないと解釈していたからです。ここに好業績企業の陥る罠があります。
企業では、“ 現在フィルム事業で儲かっているのに、なぜ、利益の上がらないデジタル化の事業に手を伸ばす必要があるのか? ” つまり、“70セントを稼ぎ出すフィルム事業を 5 セントしか稼ぎ出せないデジタル化事業に慌てて転換するのはベストではない! ” という考え方をしていました。この考え方はコダックに限らず、好業績企業の多くが陥り易い考え方です。富士フイルムもかつてこの考え方で失敗したことがありました。
一見、この考えは正しい考え方だと思われます。しかし、市場のパラダイム変換に対応しようとしたとき、企業は本来、企業の業績が良く、余裕のある時に大きく舵を切るべきなのです。経営危機に追い込まれてからでは緊急の対策に追われるあまり、本質的な対策を打つ余裕はなくなります。
その意味で、常に時代の潮流を洞察し、変化の兆しを的確に把握する予知能力と、余裕のある時に機会を捉えて思い切ったパラダイム転換をはかることが必要になるのです。
②イノベーターのジレンマ
優良企業は、既存の顧客や投資家のニーズを重視するがゆえに、評価が未知の、リスクの大きい、効率の悪い新技術への投資に対しては消極的になる傾向があります。たとえ、将来的に大きな可能性を有した技術であっても、顧客や投資家が望まない投資行動を排除する論理が優先されるのです。
新技術は、当初、小規模市場から受け入れられるので、大企業や短期リターンを重視する投資家は、小規模市場が成長するまで待つことを嫌がり、そうした市場に参入したがりません。新技術が成長して既存技術を脅かす破壊的技術に変わった時、これをうまく取り込めなかった大規模な優良企業が市場から駆逐されます。
ClaytonM.Christensen は著書 で、このような現象を「イノベーターのジレンマ」と呼び、これが1980年代多くの業界で生じていたことを事例を挙げながら報告しています。1990年代後半から2010年代までのデジタル技術革新に対するコダックの対応も、このような現象の典型的な例として理解されます。
③閉鎖的な企業環境・企業文化、自己満足の文化
銀塩写真の技術開発への積極的な投資、製造への厳密なアプローチ、そして、Lochester という地域社会と良好な関係を維持して行きたいというコダックの願望から生じたこだわりが、自己満足を招き、コダックは閉鎖的な企業環境に陥ったと言えます。1984 年のロスアンジェルス・オリンピックのスポンサー契約に関してコダックが契約に躊躇している間に、“ コダックに追いつき追い越せ ” を掲げて追撃していた富士フイルムは、オリンピック委員会とスポンサー契約を結び、その存在感を世界にアピールしていきました。
富士フィルムの対応と特徴
①時代潮流の洞察と対応
富士フィルムは、常に、時代の潮流を洞察し、将来の姿を予測し、変化を恐れずに変化に積極的に対応しました。 富士フイルムは、デジタル化という時代潮流のもとでの価格競争を含む激しい企業間競争が収益性の低い厳しい闘いになることを、理解していました。しかしながら、デジタル化は、時代の潮流なのでこれに積極的に対応することが必須であるとの考えから、これを積極的に推進しました。
こうした対応が、以後の医療・オフィス・デジタルカメラなどの分野でのデジタル機器の開発に大いに生かされ、今日の強さを支えていると言えます。
②危機意識
経営陣が日頃から時代潮流の洞察を的確に行っていたので、デジタル化に対しても深刻な危機意識を共有していました。デジタル化は経営方法を大きく変え、これまでの銀塩写真のような収益は上がらないことも覚悟していました。 こうした心の準備を事前に持っていたことによって、危機に際して迅速に構造改革を断行することができたと考えられます。
③社風・企業文化
富士フイルムは、“ コダックに追いつき追い越すこと ”を目標に、研究開発を積極的に推進してきました。創業以来富士フィルムは、研究開発を重視するという社風・企業文化を有していました。しかし、パラダイム変換に対応するべく、1つの考え方に固執せずに、多様性を尊重し、自社の保有技術を水平展開する方向に転換しました。
また、富士フイルムは、自社の成長を追求するだけではなく、一企業の範囲を超えて写真文化を大切にするという文化的価値観も持っています。東日本大震災で流失・損傷した被災者の写真を再生する活動を通じて、被災者に寄り添い彼らの苦痛を和らげ、歴史の記録を後世に残すという写真文化の重要性を改めて再確認しています。
④企業ビジョン
経営トップが企業ビジョンを明確にし、機会を捉えて内外に明示しました。富士フィルム古森社長は「21世紀を通じてリーディングカンパニーとして生き続ける」という富士フイルムの将来ビジョンを明示し、「Vision75」でその基本方針を内外に示しました。それを既存技術の棚卸しの実施と事業ドメインの構築でさらに具体化させました。
経営危機に陥っている他の企業の構造改革の発表内容を見ていると、「自分の会社がどのような方向に進もうとしているか」のビジョンが全く示されずに、目先の(短期的な)目標達成に目を奪われている場合が少なくないと言えます。変化の時代に、自社の経営資源を活用してどのような経営を目指そうとしているかのビジョンを示すことが極めて重要だと言えるでしょう。
デジタル化への変化に対する両社の対応
以上のことから両社のデジタル化への対応には、大きな差が生まれました。
コダックと富士フイルムの対応の違いには、変化への洞察力と基本的姿勢の違いが大きく影響していると考えてられます。
デジタル化が時代の潮流になることを両企業とも認識していたが、そのインパクトを楽観的に受け止めるか、悲観的に受け止めるかで、危機意識の違いになって現れていると言えます。この違いの背景には、自企業の強みと弱み、企業文化・企業風土が大きく影響していると考えられます。
自企業の強みと弱みについて、コダックは銀塩写真で技術的にも経営的にも世界一のゆるぎない地位を確立していたので、技術的にも経営上何ら問題はなかったと考えたのでしょう。 コダックにとっては、現状を維持することが重要な戦略であり、変化に対する姿勢としては、当然、消極的・否定的でした。
一方、「コダックに追いつき追い越せ」を目標にしていた富士フイルムは、現状維持ではいつまでも世界 No.2 の地位を打破できないと考えていました。研究開発力、経営力を高めて世界に打って出るためには、変化を自ら起こす必要があるから、変化に対して肯定的、むしろ、変化を積極的に追求する必要がありました。コダックと異なり、富士フイルムはデジタル化のインパクトを深刻に受け止めていたが、これに前向き・積極的に対応することが必要であるとも考えていました。
このことを含めて、富士フイルムは自社の置かれている状況から、変化に肯定的、むしろ、変化を追求する行動を志向していたと言えます。
その結果、富士フイルムは、破壊的技術の到来をバネに関連事業への多角化を進め、複写機、デジタルカメラ、電子部品・電子材料など、蓄積された技術の周辺で応用分野を広げる形での事業・商品の広範な多角化によって生き残りに成功しました。
現在、富士フイルムでは主力のフィルム事業から脱却し、医薬品、化粧品やサプリメント、医療機器、再生医療、バイオ医薬品開発を事業としています。
一方、コダックは、企業買収という形で事業の多角化を図ったが、社内技術の深耕や幅の拡大にはそれほど熱心ではなく機動的で大胆な経営を避けました。その結果、倒産という結末に陥ったのです。
つまり、この両者の経営姿勢の差が会社の破綻と成長の命運を分けたのです。
まとめ
今日では、コロナ渦の影響もありIT化が急速に進んでおり、「DX(デジタルトランスフォーメーション)時代」が到来したと言われています。DXとは、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること(経済産業省の定義)」を意味します。つまり経営者は、コロナ禍によるパラダイムシフトの渦中にいることを自覚する必要があるのです。事業承継の際、経営革新を行う際、パラダイムシフトの変換にどのように対応するかどうかが会社の行く末を左右します。是非当記事で紹介したコダックと富士フィルムの事例を参考にしていただければと思います。
※DXを導入した企業のにおすすめ記事
「事業承継はDXのチャンス? 呉服屋の七代目が特注品のネット受注で失敗したワケ」
著者 葛谷篤志 掲載日2021年9月28日(【長寿企業大国ニッポンのいま】事業承継はDXのチャンス? 呉服屋の七代目が特注品のネット受注で失敗したワケ (1/2ページ) – SankeiBiz(サンケイビズ):自分を磨く経済情報サイト)
参考文献:「変化の時代の経営パラダイム転換 -コダックと富士フイルムに学ぶ-」 著者 日下泰夫 、平坂雅男 (https://core.ac.uk/download/pdf/233125096.pdf)