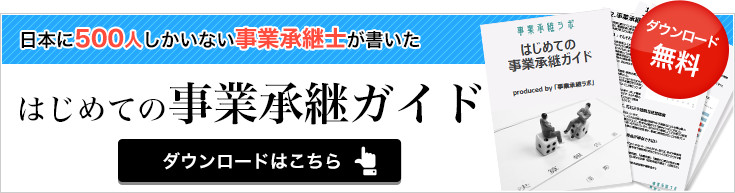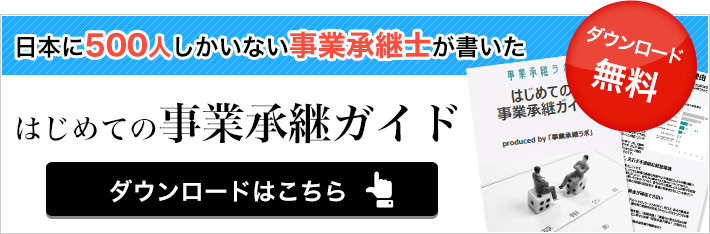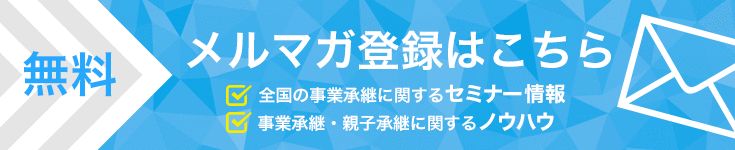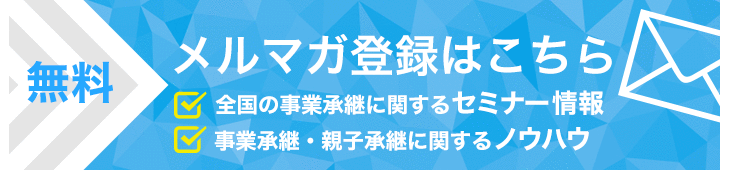創業は2017年。現場主義を貫くeel税理士法人は、法人税・相続税業務に加え、事業承継コンサルティングにも力を注いでいます。静岡と東京の二拠点で活動する代表・望月様に、開業の経緯や地方にこだわる理由、そして今後のビジョンを伺いました。
- 1. 税理士を目指したきっかけは何だったのでしょうか?
- 2. 「eel税理士法人」という名前の由来には、どのような思いが込められていますか?
- 3. 法人化にはどのような経緯がありましたか?
- 4. 現在の主な事業内容や強みについて教えてください。
- 5. 望月様ご自身の強みは、どのような点にあるとお考えですか?
- 6. 事業承継支援における、税理士とマーケターの役割分担について教えてください。
- 7. 今の事業承継支援の在り方について、感じている課題はありますか?
- 8. 事業承継支援のやりがいや原動力について教えてください。
- 9. 支援している企業の規模や業種について教えてください。
- 10. 事業承継ラボの読者へメッセージをお願いします。
税理士を目指したきっかけは何だったのでしょうか?
私が税理士を目指したのは、実はごく自然な流れの中での選択でした。多くの方が「税理士になりたくてこの道を志した」と語るのに対し、私は就職活動すらしていないまま、なんとなく進路に迷っていた大学時代。
そんな私に、父親が「やりたいことがないなら税理士事務所にでも入ってみたらどうだ」と声をかけてくれたのがきっかけです。というのも、父はかつて中堅企業の経営者でありながら、若い頃に税理士事務所で働いた経験があったからです。その経験が、彼の経営人生にとって非常に役立ったという話を聞いていたため、父の紹介で税理士事務所に就職しました。
当初は大きな目的もなかったものの、数年働くうちに「せっかくこの世界に入ったのなら、自分の名前で勝負してみたい」という想いが芽生え、資格取得と独立を決意しました。ですから、私にとって税理士という職業は“計画通り”ではなく、“ご縁と流れ”の中で出会った職業なんです。
「eel税理士法人」という名前の由来には、どのような思いが込められていますか?
実はこの「eel(イーイーエル)」という社名には、少しユニークな背景があります。私の実家は、私が生まれる前に元々うなぎ屋を営んでおり、呉服屋に商売を変えたあとも「うなぎや洋品店」という屋号で商売をしておりました。その名残と想いを込めて、独立の際に「うなぎ」をどこかで使いたいと考えていたんです。母から「英語で“うなぎ”ってeelだよ」と言われ、それがきっかけで「eel税理士事務所」という名称をつけました。
でも、ただの洒落では終わらせたくなかったので、名刺のデザイナーと一緒に「enrich each life(それぞれの人生を豊かに)」という意味を後付けしました。これは、私自身が大切にしている価値観でもあります。税理士として関わる相手が一人ひとり異なる人生や経営課題を持っているからこそ、その人に合った最適な支援をしたい。そんな思いを込めたネーミングです。表向きはスマートに見せつつ、実は家業の想いがしっかりと根付いている社名なんですよ。
法人化にはどのような経緯がありましたか?
税理士法人を設立するには、最低でも税理士が2名必要です。私は2017年に個人事業主として独立開業しましたが、より大きなフィールドでクライアントの課題に向き合っていきたいという想いから、半年後にパートナーと共に法人化することを決断しました。個人事業ではどうしても属人的になりがちで、組織としての体制や仕組みが整いづらい面もありました。法人化によって人材を育成しやすくなり、チームとして知見を深めながら業務の幅を広げられるようになったのは大きな変化でしたね。
今では、各分野のプロが揃う組織として、より複雑な経営課題にもワンストップで対応できる体制を整えています。
現在の主な事業内容や強みについて教えてください。
eel税理士法人には大きく3つの事業柱があります。
1つは法人税や個人事業主の所得税申告を扱う、いわゆるスタンダードな税務顧問業務。
2つ目は、相続税に特化した専門部署です。遺産分割や節税提案など、資産税分野に強みを持っています。
そして3つ目が、私がメインで担当している「事業承継コンサルティング」。これは単なる税務の枠を超えた支援です。以前、私は事業再生の現場で約3年間、企業経営の立て直しに携わっていました。会社が傾き、社員や経営者が苦しむ現場に身を置き、早期退職制度・再就職支援・取引先対応など、数字では見えない“現実”と向き合ってきました。その経験があるからこそ、税理士という立場でも経営者にとって本当に意味のある、実行可能な提案ができると自負しています。現場感を持つ税理士はまだまだ少ない。そこが私たちの強みです。
望月様ご自身の強みは、どのような点にあるとお考えですか?
やはり一番の強みは、「現場を知っていること」だと考えています。私はこれまで、机上で数字を扱うだけでなく、実際に経営の現場に入り込み、事業再生の中で汗をかいてきました。深夜まで社員と話し込み、取引先に頭を下げ、時には人員整理や再就職支援まで行いました。そうした「わちゃわちゃした現場」を経験している税理士は、正直少ないと思います。
だからこそ、一般的な税理士とは違う視点で支援ができる。数字と現実の両面を見ながら、経営者の孤独や悩みに寄り添える存在でありたいと思っています。
地域としては静岡と関東圏が中心とのことですが、地方に注目されている理由は何ですか?
私自身、静岡出身ということもあり、地元の経営者とのご縁が自然と生まれてきました。東京の方が事業承継問題の案件数は多いかもしれませんが、地方の中小企業は後継者不足や人材難といった、より深刻な問題を抱えています。地方には良い商品や技術があるにもかかわらず、それを活かす「経営者」や「情報発信」が足りていない。そういった現状をどうにかしたいという想いから、地方の事業者に対してより丁寧にアプローチするようになりました。
また、連携しているマーケターも地方支援に強い想いを持っており、一緒に“地方の底上げ”に取り組む姿勢を大切にしています。
事業承継支援における、税理士とマーケターの役割分担について教えてください。
税理士である私が担うのは、財務や税務、そして経営全体の見立てです。それに対してマーケターは、市場環境や商品価値、ポジショニングの分析を担ってくれます。
実は、中小企業の多くは「自分たちのことをよく知らない」という問題を抱えています。従業員の平均年齢、業界内の立ち位置、市場の広がりなどを把握できていない経営者は非常に多い。だからこそ、まず「自社を知る」というプロセスが必要なんです。
私たちは調査報告書という形で、現状を可視化することから始めています。経営者が自分たちの強みと課題を理解した上で、次の一手を一緒に考えていくスタイルをとっています。
今の事業承継支援の在り方について、感じている課題はありますか?
事業承継というと「株の移転」や「節税スキーム」に目が向きがちですが、それだけではうまくいきません。事業の本質や、経営者の想い、従業員の理解、今後の成長戦略までを含めた“包括的な承継”が必要です。
ところが現状では、専門家が部分的にサポートする形が多く、全体をまとめる司令塔がいない。それを担えるのが、私は税理士だと思っています。財務・税務に強く、経営全体を見渡せる立ち位置にいる税理士こそ、事業承継の舵を取るべきだと考えています。専門家同士がもっと連携して、横断的な支援をしていく仕組みをつくることが、今後ますます求められると思います。
事業承継支援のやりがいや原動力について教えてください。
やはり経営者から直接悩みを打ち明けられ、それに対して伴走型で支援できることが一番のやりがいです。経営者というのは、常に孤独を抱えています。特に事業承継という人生の大きな決断を前にしたとき、誰にどう相談していいか分からない人が多い。そんなときに、信頼できる存在として傍にいられること、そして「あなたに相談してよかった」と言ってもらえることが、私の原動力になっています。
支援している企業の規模や業種について教えてください。
業種は問わず、製造業、建設業、サービス業など幅広く対応しています。規模感で言えば、売上で3億円以上、従業員数で30~100人程度の中堅企業が中心ですね。東京もありますが、実際は地方企業の割合が多くなっています。
地方での税理士不足や、事業承継支援の人材課題についてどうお考えですか?
税理士の数自体は足りていると思いますが、事業承継のような高度で責任の重い支援を本気でやりたがる税理士は正直少ないです。というのも、関わる金額も大きく、提案の失敗が企業の命運を分けることもある。
だからこそ、リスクを避けたがる傾向があるんですね。でも私は、むしろその難しさの中に価値があると思っています。顧問税理士との協業による新しい支援の形も模索しながら、事業承継の専門性を広げていけたらと考えています。
事業承継ラボの読者へメッセージをお願いします。
事業承継は、経営者にとって人生で一度きりの大仕事です。不安や戸惑いはあって当然。でも、そんなときに誰かに相談することで、道が拓けることもあります。「こんなこと相談していいのかな」と思わず、まずは気軽に声をかけてください。私たちのノウハウが、あなたの事業と人生に少しでも役立てれば嬉しいです。