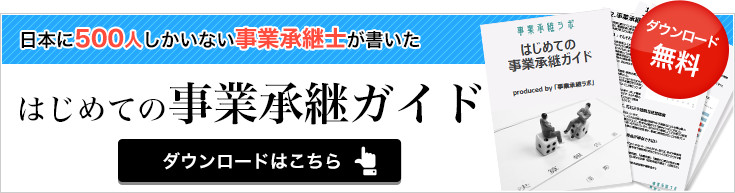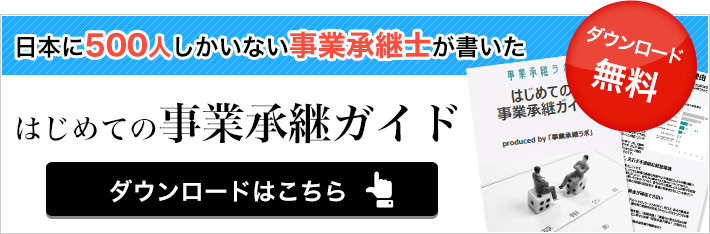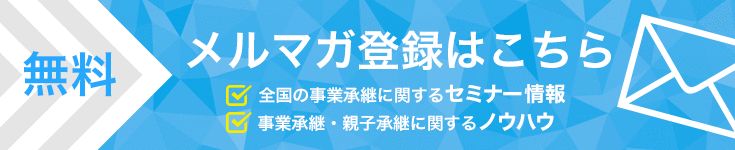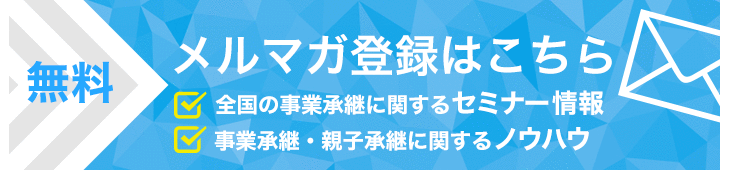軍手製造から始まり、今やEC・オリジナルプリント軍手を販売する軍手工房を提供する「株式会社イナバ」。創業65年を迎えた老舗企業の挑戦と、三代目・稲葉さんの歩み、そして事業承継のリアルに迫りました。
- 1. まず、株式会社イナバの事業概要を教えてください。
- 2. 創業当時からの事業の変遷について教えてください。
- 3. 軍手工房というブランド名を掲げられていますが、御社の強みを教えてください。
- 4. 名入れ軍手など、カスタム対応もされていると伺いました。
- 5. EC比率が高くなっているとのことですが、展開の工夫などあれば教えてください。
- 6. 稲葉さんが家業に戻られた経緯について教えてください。
- 7. 印象に残っている取り組みやエピソードがあれば教えてください。
- 8. 事業運営の中で困難だった経験についても教えてください。
- 9. 後継者としての挑戦について教えてください。
- 10. アトツギ甲子園やアトツギジャンプといった新規事業支援プログラムに参加され何を開発されていらっしゃいますか。
- 11. 今注力している事業や、今後の展望について教えてください。
- 12. 事業承継に向けた準備について教えてください。
- 13. 将来的に目指す会社の姿を教えてください。
- 14. 最後に、事業承継ラボの読者へのメッセージをお願いします。
まず、株式会社イナバの事業概要を教えてください。
弊社は昭和35年創業で、今年で65年を迎えます。創業以来、軍手の製造と販売を主軸に事業を展開しており、現在は自社製品の販売に加えて、海外製の軍手の輸入・販売、名入れ対応の販促品、そしてホールガーメント機による新商品の開発など、幅広い商品を展開しています。
製造から販売、発送まで一貫して自社で行っているのが大きな特徴で、効率的かつ高品質な製品提供を実現しています。
創業当時からの事業の変遷について教えてください。
もともとは久留米市の水天宮境内で履物屋としてスタートしました。下駄などの履物を販売していた時代、取引先の履物店の要望から軍手の製造を始めたのがきっかけです。
その後、時代の流れに合わせて事業を拡大し、約30年前からはホームセンター向けの卸事業に注力。さらに海外製品との価格競争を背景に、海外提携工場での生産にも取り組みました。
近年はEC市場の拡大を見越して、父がECサイトを立ち上げ、現在ではECと卸の二本柱で事業を展開しています。
軍手工房というブランド名を掲げられていますが、御社の強みを教えてください。
最大の強みは、自社で製造から販売まで一貫して行える体制です。中間業者を介さないため価格面でも優位性があり、品質管理にも徹底して取り組める点が魅力です。
特に13ゲージという細かな編み目の軍手を国内工場で製造しており、手にフィットし、機能性にも優れています。自社サイトの運営もすべて内製化しており、ユーザーの声を即座に反映できる柔軟さも当社ならではです。
名入れ軍手など、カスタム対応もされていると伺いました。
名入れ軍手は、地域性と顧客ニーズを組み合わせた結果生まれた商品です。久留米は名入れタオル文化がある土地で、その発想を軍手に応用しました。13ゲージの細かな編み目により、高精細なプリントが可能となり、販促品として多くの企業様にご利用いただいています。温泉施設や銀行、建設会社、イベント団体など、幅広い業界での導入実績があり、Instagramでもその一部を紹介しています。
EC比率が高くなっているとのことですが、展開の工夫などあれば教えてください。
現在は売上の過半数をECが占めており、自社サイトの他、楽天やAmazonといったモールでも販売しています。Google広告などの運用も自社で行っており、デジタルマーケティングを駆使した集客にも取り組んでいます。
特にBtoB向けの提案が中心ですが、ECの特性を活かしてBtoCの販路拡大も積極的に図っています。
稲葉さんが家業に戻られた経緯について教えてください。
大学を中国・上海で卒業予定だったのですが、単位不足で卒業が一年延期になってしまい、就職活動がうまくいかず、インターンなどを通じて自然と家業に入る流れとなりました。
最初からEC部門に携わり、サイトのリニューアルや広告運用、ブランディングに取り組みました。大学ではグラフィックデザインを学んでいたため、その知見を活かしてクリエイティブ面でも貢献しています。
印象に残っている取り組みやエピソードがあれば教えてください。
やはりホールガーメント機の導入は大きな転機でした。無縫製で製品が作れるため、ニット製品の可能性が広がり、アパレルとの連携や新商品の開発にもつながりました。
また、名入れ軍手も、お客様のニーズに応えながら進化させてきた商品で、提案の幅が広がっています。
事業運営の中で困難だった経験についても教えてください。
海外工場からの仕入れ品に不良品が発生した際は、全数検品を行い、品質管理体制の見直しを迫られました。
現地での検品ルールを構築し、現場指導も徹底するなど、信頼回復に向けて全社一丸で対応しました。トラブルはあったものの、それをきっかけに仕組みづくりの重要性を再認識しました。
後継者としての挑戦について教えてください。
私は比較的自由にチャレンジできる環境を与えられてきました。父も新しいことに積極的なタイプで、私がECや商品開発に取り組むことに対して否定的な反応はありませんでした。後継ぎとして、名入れ軍手の提案や、カラー展開の導入、EC戦略など自分の感性とデータに基づいて改善を重ねています。
アトツギ甲子園やアトツギジャンプといった新規事業支援プログラムに参加され何を開発されていらっしゃいますか。
1年目は、職人が使用する軍手に企業ロゴをプリントする「職人スポンサー」というアイデアで参加しました。職人がSNSや映像で露出する機会が増える中で、ロゴ入り軍手が広告媒体になるという発想です。
2年目はホールガーメント機を使い、アスリートの手を3Dスキャンして最適化した補助手袋の構想を発表しました。どちらも、可能性のある実践的な試みでした。
今注力している事業や、今後の展望について教えてください。
今は名入れ軍手のさらなる認知拡大と、保湿手袋の開発に注力しています。特に保湿手袋は、手荒れに悩む女性や医療・介護分野などでも需要があり、他の後継ぎ企業と連携して開発中です。軍手を単なる作業用品ではなく、「選ばれる商品」へと昇華させることを目指しています。
事業承継に向けた準備について教えてください。
株の引き継ぎや金融機関との関係構築など、外部的な要素の整備を進めています。見えない部分では、父と日々情報共有しながら経営感覚を磨いています。正式な承継時期は未定ですが、事業承継には資金も時間もかかるため、適切なタイミングでの実施を目指しています。
将来的に目指す会社の姿を教えてください。
現在は家族経営中心の体制ですが、今後は正社員を採用して持続可能な組織体制を築きたいと考えています。繊維産業の多くはパート依存ですが、安心して働ける環境づくりと、若い世代が活躍できる現場づくりを目指しています。
最後に、事業承継ラボの読者へのメッセージをお願いします。
アトツギとして大変なことはたくさんありますが、今は仲間とつながれるコミュニティがある時代です。悩みやアイデアを共有できる仲間の存在はとても心強いです。ぜひ他の後継ぎとも積極的に交流しながら、挑戦し続けてほしいと思います。