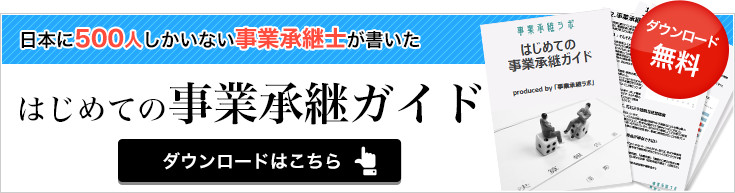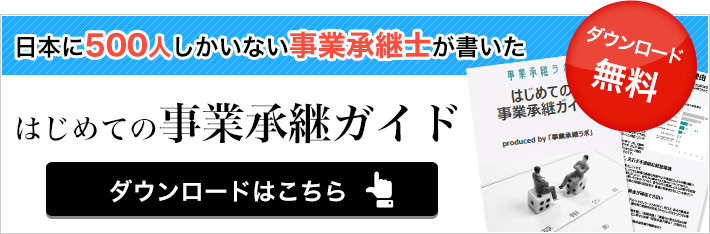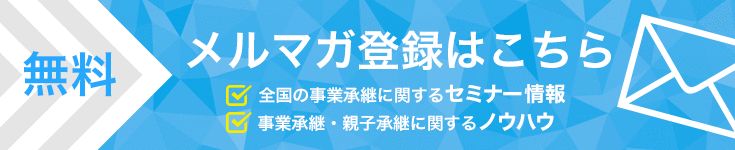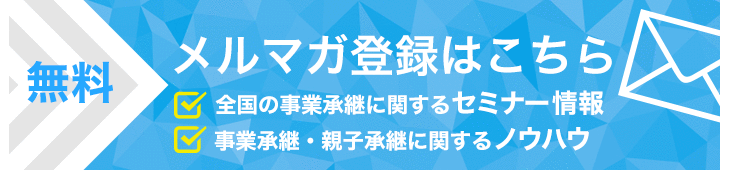広島県安芸高田市で30年親しまれてきた「ラーメン霧切谷」。その外観や雰囲気を残しつつ、株式会社ホッツッが「八千代きりちゃんラーメン」として再出発しました。単なる店舗の継承ではなく、地域に根付いた“情景”を未来へ繋ぐ新しい挑戦について、代表の渡部崇さんに伺いました。
まず、渡部さんのこれまでのご経歴を教えてください。
私は広島生まれで、飲食業界に携わって18年ほどになります。最初は広島のご当地グルメである汁なし担担麺に注目し、店舗展開を進め、最大で17店舗まで広げることができました。当時はまだ知名度が高くなかった麺料理を、県内外に広めることを目標に、東京や大阪、福岡など都市部にも出店しました。その過程では、アンテナショップへの出店やカップ麺の商品化など、さまざまな手法で「広島の食」を全国に届けることに挑戦しました。
そうした経験の中で、“自分が美味しいと感じたものを広島から全国へ”という思いが自然と芽生え、食を通じて地域と地域をつなぐことをライフワークとしてきました。2年前に汁なし担担麺事業からは離れ、現在は株式会社ホッツッを立ち上げ、広島に新しい挑戦を仕掛けています。
「ラーメン霧切谷」を引き継ごうと思われた経緯をお聞かせください。
正確には、霧切谷を「事業承継」したわけではありません。土地自体は国土交通省の所有で、商工会が管理するプレハブ施設の一角でした。元々は商工会の女性部がうどんやラーメンを提供する場として始まり、地域の方が長年切り盛りしてきましたが、高齢化に伴い閉店となりました。
その後、「この建物をどう活かすか」という話が商工会で上がっていると私の耳に入りました。私は以前よりツーリングの途中などでこの建物をよく目にしており、そこにあることが風景の一部になっていると感じていました。だからこそ「ただ壊して新しいものを建てる」のではなく、風景や思い出ごと残すことに価値があるのではないかと考え、この場を新しい形で再生することに決めました。
今回掲げられた「情景承継」という言葉には、どのような想いが込められていますか。
飲食業界では「居抜き」で始めるケースがよくありますが、多くはコストを抑えるためという事業者目線の理由にすぎません。私はそこに違和感を持っていました。地域にとっては、建物や外観は単なる器ではなく、日常の中に溶け込んだ風景です。
たとえば通勤やツーリングで通る人にとって、そこにラーメン屋があること自体が安心感であり、暮らしの一部なのです。だから外観はそのまま残し、違和感を持たれないよう配慮しました。厨房機器は一新しましたが、それはあくまで裏方。見た目や雰囲気は30年続いた当時のままを意識しました。単なる「事業承継」ではなく、土地に根付いた風景や空気感ごと未来へ繋ぐことを目指し、「情景承継」という新しい言葉を掲げています。
守ったものと、新しく挑戦したものは何でしょうか。
守ったのは「外観」と「地域との関係」です。地方で新しい店を出す際、よそ者が排他的に扱われることは少なくありません。だからこそ、ご近所への挨拶や掃除を積極的に行い、商工会からの依頼にも協力し、地域の一員として信頼を積み重ねることを大切にしました。
一方、新しく挑戦したのは、「同じく地域を大切にする」という理念を持つ「ちゃんのれん組合」への加盟です。私もファンになった東京発祥の“ちゃん系ラーメン”という最先端の味を広島の山奥で提供することで、近隣のお年寄りが自然にその味を口にする。本人たちは気づかなくても、実は東京でしか食べられない本格的な味を体験している。この“最先端と地域の生活が交わる瞬間”に面白さを感じています。伝統を守りながら新しい価値を仕込む、このバランスこそが今回の挑戦です。
お店づくりで特に工夫された点は何でしょうか。
最大の工夫は「誰もが迷わず楽しめる設計」にすることでした。メニューは中華そば、チャーシューメン、ネギ中華そばの3種類に限定。高齢のお客様でも券売機の前で悩まずに注文できるようにしています。券売機自体もタッチパネルではなく、大きなボタン式。キャッシュレスにも対応せず、あえて昔ながらの使いやすさを残しました。手ごろな価格にし大盛りも用意せず、ご飯を無料にして「ラーメンライス」を楽しんでもらう工夫もしています。実は広島ではラーメンとご飯を一緒に食べる文化が薄いのですが、無料にすることで自然にその体験をしてもらえるようにしました。見た目は昔のままのラーメン屋ですが、厨房は最新設備で効率化されており、裏側では新しいノウハウを活かしています。外観は古く、中身は最新。これが今回のこだわりです。
オープン後の反響はいかがですか。
オープンからすぐに予想を大きく上回る反響をいただきました。6席しかない小さな店に、土日はオープン前から30人以上が並ぶ事もあります。驚いたのは、以前一度も入ったことがなかった地元の方々が「再開したんだね」と足を運んでくださることです。建物や外観がそのまま残っていたからこそ、「新しいのに懐かしい」と感じてもらえたのだと思います。外観を守ることが、お客様の記憶や思い出とつながり、新たな来店動機になっている。数字以上に、地域の人たちが笑顔で戻ってきてくれることが、この挑戦の成果だと実感しています。
「八千代きりちゃんラーメン」を通じて、地域にどんな価値を届けたいと考えていますか。
私が目指すのは「賑わい創出」ではなく、「出ていく理由を減らす」です。地方は人口減少が進み、「この町には何もない」と若者が出ていく現状があります。でも実際には魅力や価値がたくさん埋もれています。東京の最先端のラーメンを山奥で食べられるという驚きが、「自分たちの町も悪くない」と感じるきっかけになる。
ビジネスとして成功すること以上に、地域の誇りを取り戻すことが大切だと考えています。実際、開業から短期間で地元の高校生がアルバイトに応募してくれたり、その友人を紹介してくれたりと、人のつながりも広がり始めています。「情景を守ること」が、地域の新しい未来につながるのだと信じています。
今後の展望を教えてください。
今後は「八千代きりちゃんラーメン」を軸にしながら、広島に新しい食文化を根付かせたいと考えています。その一つが、かつて日本中で親しまれた「夜鳴きそば」の復活です。軽トラで夜中に街を回り、ラーメンを提供する文化は今やほとんど消えつつあります。これを最新のスープや技術を取り入れつつ、昔の風景そのままに復活させたい。表の顔は「情景承継」を体現する店舗、裏の顔は「夜鳴きそば」という新たな挑戦。この二つを両立させ、広島から地域と食文化の可能性を発信していきたいと考えています。